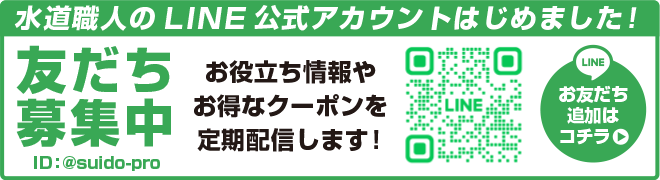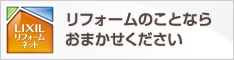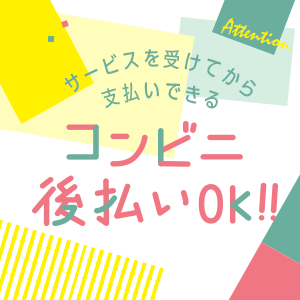水のコラム
たくさんある!春に降る雪「名残雪」の種類【水道職人:公式】

「名残(なごり)雪」をご存じですか?
1976年に発売された、イルカさんのなごり雪という歌で、言葉としては浸透していますが、その意味についてはあまり知られていないでしょう。
名残雪とは、春が来ても消えずに残っている雪や、春が来てから降る雪のことを指します。
また、名残雪は春の季語としても用いられます。
そんな名残雪には種類が複数あり、それぞれが持つ意味も異なるでしょう。
今回は、名残雪についてご紹介します。
名残雪①淡雪

「淡雪(あわゆき)」とは、春先に降るうっすらと積もる程度の、すぐに溶けて消えてしまう雪のことです。
「久保田万太郎さん」の俳句にも登場する、春の季語です。
淡雪は「牡丹雪(ぼたんゆき)」や「綿雪(わたゆき)」とも呼ばれています。
淡雪には、雪の結晶同士がいくつもつながり、雪片(せっぺん)となって降り積もる特徴があります。
また、近年では鹿児島県で淡雪という名前のいちごが育種(いくしゅ)されているため、いちごの名前として憶えている方もいらっしゃるかもしれません。
名残雪②斑雪

「斑雪(はだれゆき/まだらゆき)」は、斑に降り積もった雪や、斑に消え残った雪のことです。
斑雪は、「万葉集その六百七十四 (はだれ)」にも春の季語として登場します。
斑雪には三つの意味があります。
一つ目は、降り積もった後に斑に残っているという意味で、二つ目は、日陰に斑に残っているという意味です。
そして三つめは、ほろほろと斑に降り積もる雪という意味で、この三つ目の意味合いで平家物語にも使われています。
名残雪③雪の果

「雪の果(ゆきのはて)」とは、雪の降り納めに降る雪のことです。
「降りじまいの雪」とも呼ばれています。
なお、太陰暦の2月15日には、釈迦牟尼(しゃかむに)が入滅(にゅうめつ)した日に行う法会である涅槃会(ねはんえ)が執り行われます。
この涅槃会の前後に降る雪ということで、「涅槃雪(ねはんゆき)」とも呼ばれているのです。
雪の果は、「石田波郷(いしだはきょう)さん」の「雨覆(あまおおい)」にも登場する春の季語です。
名残雪④雪間

名残雪には、「雪間(ゆきま)」も含まれます。
雪間には三つの意味があるでしょう。
一つ目は、雪が降り止んでいる間や、雪の晴れ間のことです。
二つ目は、降り積もった雪の所々にある雪が消えた部分のことで、「尾崎紅葉さん」の俳句に登場する春の季語でもあります。
三つめは、雪が降っている中や雪が降り積もった中のことで、「新撰和歌六帖(しんせんわかろくぢょう)」に登場する春の季語です。
名残雪⑤残る雪

「残る雪(のこるゆき)」は消え残った雪のことで、春になっても消えずに残っている雪のことを指します。
「残雪(ざんせつ)」とも呼ばれており、こちらの呼び方の方が有名かもしれませんね。
残雪は「文華秀麗集(ぶんかしゅうれいしゅう)」に春の季語として使われています。
また、残る雪も「連歌至宝抄(れんがしほうしょう)」に春の季語として登場します。
どちらも同じ意味合いではありますが、書き手によって選ぶ単語が異なるようです。
名残雪⑥雪代

「雪代(ゆきしろ)」とは、川に流れ出た溶けた雪水のことです。
雪代の中には「雪濁り(ゆきにごり)」や「春出水(はるでみず)」も含まれるでしょう。
雪濁りとは雪の影響で川や海が濁ることを指し、春出水は雪代の影響で洪水が起こることを指します。
春出水の規模が大きくなると、災害となり人々の生活に影響を与えることもあるでしょう。
雪代は「沢木欣一(さわききんいち)さん」の俳句に登場する、春の季語です。
名残雪⑦雪解

「雪解(ゆきげ)」とは、雪が解けることで、雪解けとも呼ばれています。
雪解は「万葉集」に登場する春の季語ですが、雪とは関係がない場面でも雪解けは使われることがある単語です。
国際間や個人間などの緊張感が緩和する際に、雪解けという言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃると思います。
このように、和解の空気が生じた場合にも用いられることがあるのです。
京都には雪を模したお菓子がある!

京都には冬の間だけ販売されている和菓子が複数あります。
その中でも一押しなのが、「 亀屋良長(かめやよしなが)株式会社」の「暦(雪こんこ)」です。
こちらのお菓子は真っ白な色彩で雪だるまの形をしており、口の中に入れると雪のようにスッと溶けていくことが特徴です。
和三盆が使われているため、甘くなりすぎない上品な甘さも魅力と言えるでしょう。
また、暦(雪こんこ)は、公益社団法人 京都デザイン協会が行っている京都デザイン賞を、2013年に受賞しています。
冬の間しか販売していないので、今年はもう購入ができません。
来年の冬のお供のお菓子候補としてご検討ください。
参考:暦(雪こんこ) | お干菓子┃亀屋良長の菓子見本帖と小噺
※本記事でご紹介している方法は、一般的な対処法の例です。
作業を行う際は、ご自身の状況や設備を確認のうえ、無理のない範囲で行ってください。
記事内容を参考に作業を行った結果生じた不具合やトラブルについては、当社では責任を負いかねます。
少しでも不安がある場合や、作業に自信がない場合は、無理をせず専門業者へ相談することをおすすめします。